| 受付番号 |
U25011 |
承認番号
|
25011A |
| 企画名 |
つくば自然共生プロジェクト~ITF Lab.~ |
| 活動分類 |
学外登録団体または学内組織・団体ボランティア |
| 活動分野 |
環境安全
|
| 活動目的 |
筑波大学の広大な自然を自然共生サイトとして登録することが活動の目的である。
本活動では、キャンパス内の動植物の調査や申請書案の作成を行い、学生から大学に自然共生サイトの登録に向けた働きかけを行う。また、つくば市内の自然共生サイト登録地域との連携を推進すべく、共生サイトの見学会・意見交換会を実施する。
近年、生物多様性の急速な消失が世界的な課題となっている。森林破壊、海洋汚染、気候変動などの影響により、多くの動植物が絶滅の危機にさらされ、生態系のバランスが崩れつつある。生物多様性は、私たちの食料・水・空気の質など、暮らしの根本を支える重要な基盤であり、これを守ることは人間社会の持続可能性にも直結している。
こうした背景のもと、国際社会は「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」という目標を掲げた。これは、2030年までに地球上の陸と海の30%以上を健全な生態系として保全し、生物多様性の損失を食い止めるとともに、回復への道筋を築くことを目的とした国際的な目標である。この目標は、2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に明記され、日本でも2023年に「生物多様性国家戦略2023–2030」に位置づけられている。
この30by30目標の達成手段の一つが自然共生サイトの登録である。自然共生サイトとは、国立公園などの法的保護地域ではないが、結果的に生物多様性の保全に寄与している区域を指す。地域や民間、大学などの主体が管理している場所であっても、生態系が守られ、管理が継続されている場合には、自然共生サイトとして認定される可能性がある。
筑波大学は、広大なキャンパスに多様な自然環境を有しており、生物多様性の観点からも重要な資源を抱えている。そのような場所を自然共生サイトとして登録することは、大学が持つ自然資源の価値を明確に示し、国内外に対して環境保全への主体的な貢献を発信することにつながる。また、学生や研究者にとっても、身近なフィールドとして自然を活用できる環境が制度的に認められることで、教育や研究の質も高まると期待される。
以上の理由から、筑波大学が自然共生サイトとして登録を目指すことは、30by30の実現に資するだけでなく、持続可能な大学経営と社会貢献の観点からも極めて意義深い取り組みである。 |
| 具体的な活動計画 |
活動内容
学生から大学に対して自然共生サイトの登録に向けた働きかけを行い、実際に登録を目指す。つくば市内の自然共生サイト登録地域との連携を推進すべく、共生サイトの見学会・意見交換会を実施する。
具体的には筑波大学、筑波キャンパス内にある自然の中から、自然共生サイトの基準を満たすエリアを選定。エリアの生物等を把握する調査を経たのちに、申請書類を作成し、筑波大学を自然共生サイトに登録する。
スケジュール
7月
チームビルディング(担当分担、役割決定)
8月 どこが登録できるか、考える。
調査(現地・大学有識者)
土地所有・管理体制の確認
つくば市内の自然共生サイト訪問(国立環境研究所、応用地質株式会社を予定)
申請書の骨子作成
9月 どこを登録すべきか考える。
調査結果の整理
申請書ドラフト作成
ERCAへの事前相談実施
10月 本格的な書類作成にとりかかる。
事前相談を受けた修正作業
必要に応じて追加調査・追記
学内合意形成(教員・施設管理関係者)
11月 書類最終段階にとりかかる。
書類の最終化
学内手続き完了
必要に応じて関係者ヒアリング調整
筑波大学生き物多様性フェスタにて活動報告
共生サイト登録に積極的なつくば市内企業等が集まる場で報告会
⇒申請書ブラッシュアップ
12月 提出。
正式申請書の提出(ERCA宛)
報告・振り返り・成果の共有 |
| 活動場所 |
筑波大学筑波キャンパス人文社会学系棟 B216
つくば市内の自然共生サイト見学させていただく可能性有り。(国立環境研究所、応用地質株式会社を予定) |
| 活動期間 |
2025/07/14 ~ 2026/01/14 |
| イベント日・時間 |
|
| 募集期間 |
2025/07/14 ~ 2026/01/14 |
| 対象者 |
学生、教職員 |
| 予定希望人数 |
10人 |
| 最低必要人数 |
5人 |
企画または
グループのURL |
|
| 企画申請者(プランナー) |
作森元司郎(人間総合科学学術院 1年) |
| 備考 |
|
| 画像 |
画像1: 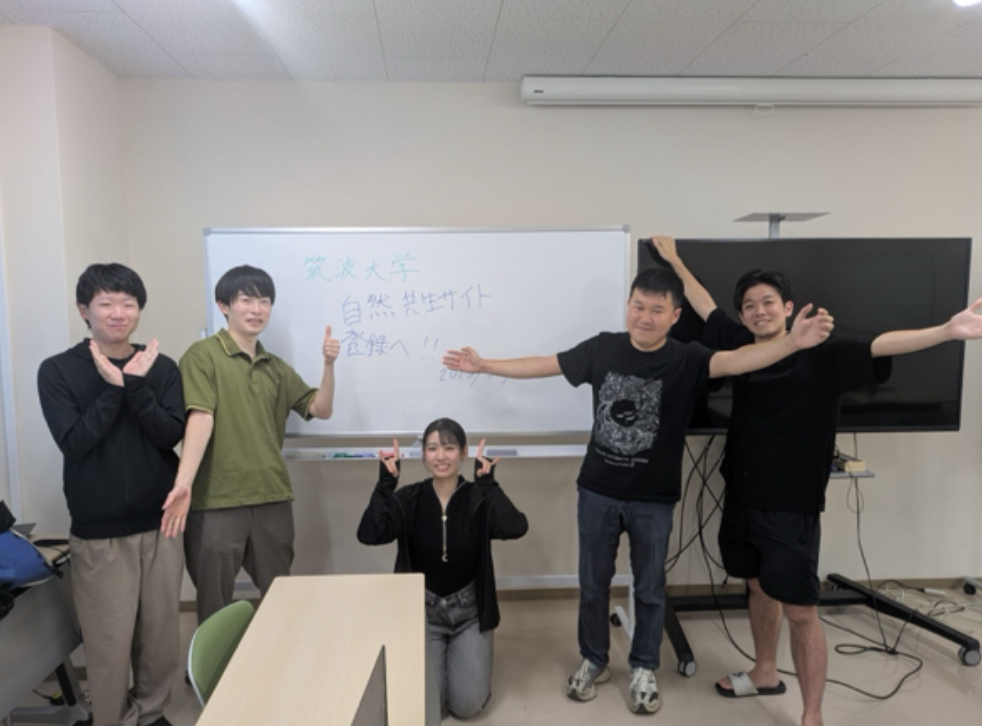 画像2: 画像2:  画像3: 画像3: 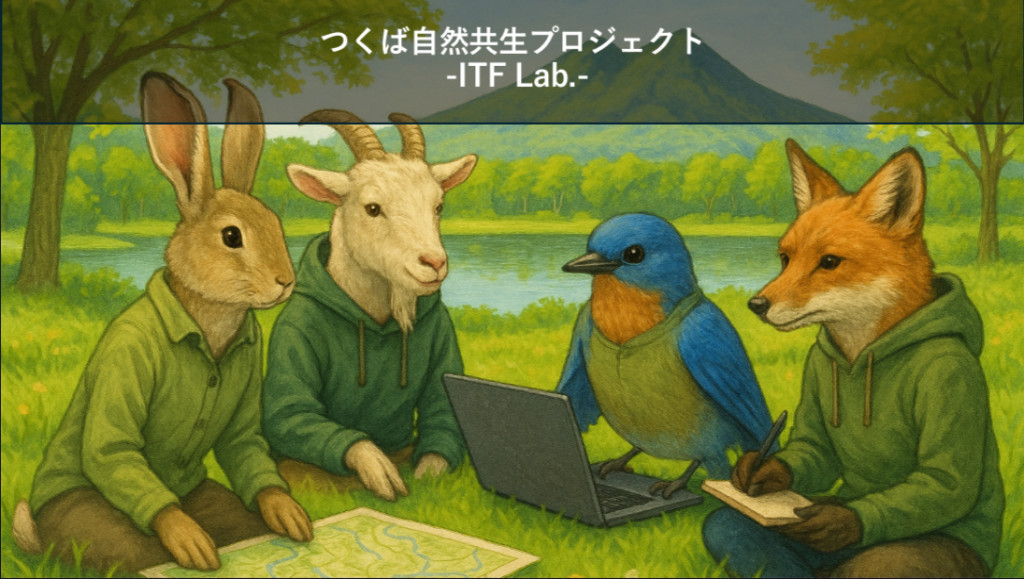 |